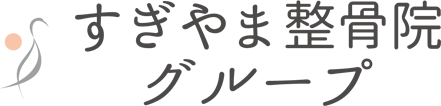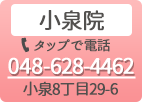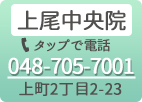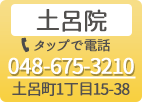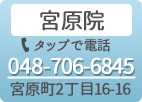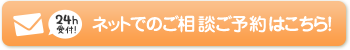野球肘(離断性骨軟骨炎)


- 肘が痛くて投げられない
- 肘の内側が腫れている
- 肘がロックされる感じがする
- 肘を曲げると痛みが走る
- 握力が弱くなった気がする
野球肘(離断性骨軟骨炎)について|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
解剖学的背景
離断性骨軟骨炎(Osteochondritis Dissecans: OCD):
- 離断性骨軟骨炎は、骨と軟骨の一部が血行不良により壊死し、最終的に骨から分離する病態です。
- 特に肘関節では、上腕骨の外側部分(肘関節の外側顆)が主な損傷部位です。
野球肘(離断性骨軟骨炎)の原因|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
野球肘(離断性骨軟骨炎)は、主に繰り返しのストレスや外傷によって肘関節の骨と軟骨が損傷し、血行不良となることで発生します。以下に、具体的な原因を詳しく説明します。
1. 繰り返しの投球動作
- 投球回数の多さ:
- 野球やソフトボールのピッチャーなどが、長時間にわたり頻繁に投球を繰り返すことで、肘関節に過度なストレスがかかります。
- 特に若年層で成長期にある選手は、骨や軟骨が発達途上のため、過剰な負荷に耐えきれず損傷しやすくなります。
- 高い投球強度:
- 投球のスピードや強さが増すことで、肘関節にかかる負荷が大きくなり、骨と軟骨にダメージを与えます。
2. 投球フォームの問題
- 不適切なフォーム:
- 正しい投球フォームを身につけていない場合、肘や肩に過度な負荷がかかりやすくなります。
- 特に肘を過度に外反させるフォームは、肘関節外側顆に大きなストレスを与えます。
- フォームの反復:
- 不適切なフォームを繰り返すことにより、慢性的なストレスが肘関節にかかり、骨と軟骨の損傷が進行します。
3. 投球頻度と休息の不足
- 過度な投球頻度:
- 短期間に大量の投球を行うと、肘関節の骨と軟骨が回復する時間が不足し、損傷が蓄積します。
- 休息不足:
- 十分な休息を取らずに投球を続けると、損傷が進行し、離断性骨軟骨炎のリスクが高まります。
4. 外傷
- 急性の外傷:
- 一度の強い衝撃や外力により、肘関節に急激なストレスがかかり、骨と軟骨が損傷することがあります。
5. 過去のケガ
- 既往歴:
- 過去に肘のケガを経験している場合、関節の構造が弱くなっており、再度の損傷リスクが高まります。
6. 発育期の影響
- 成長期の子供:
- 成長期の子供は、骨や軟骨が完全に発達していないため、過度な投球によって損傷しやすくなります。
- 特にリトルリーグや中学・高校野球での過度な投球が原因となることが多いです。
野球肘(離断性骨軟骨炎)の症状|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
野球肘(離断性骨軟骨炎)は、肘関節の骨と軟骨が損傷することでさまざまな症状を引き起こします。以下に、主な症状を詳しく説明します。
1. 痛み
- 投球時の痛み:
- 特に投球動作中やその直後に、肘の外側に鋭い痛みが生じます。
- 痛みは投球回数が増えると悪化し、休息をとっても完全には消えないことが多いです。
- 安静時の痛み:
- 症状が進行すると、安静時や日常生活の動作中にも痛みが現れることがあります。
- 肘を曲げたり伸ばしたりするだけで痛みが生じることもあります。
2. 腫れと炎症
- 肘の腫れ:
- 肘関節周囲に腫れが見られることがあります。腫れは炎症反応の一環として現れます。
- 熱感:
- 損傷部位に炎症が起こり、触れると熱感を感じることがあります。
3. 関節のロッキング
- 関節のロッキング(引っかかり感):
- 剥離した骨片や軟骨片が関節内で動くことにより、肘関節がロックされる(動かなくなる)ことがあります。
- この症状は、肘を動かそうとすると突然引っかかり、動かなくなることを指します。
4. 可動域の制限
- 肘の可動域の制限:
- 痛みと腫れにより、肘関節の可動域が制限されることがあります。
- 肘を完全に伸ばしたり曲げたりすることが難しくなります。
5. 握力低下
- 握力の減少:
- 痛みや不安定感のために握力が低下し、ボールを握ることが困難になることがあります。
- 握力低下は、日常生活にも影響を及ぼします。
6. 関節の不安定感
- 肘の不安定感:
- 骨片が剥離することで関節が不安定になり、特に投球動作での外反ストレスに対する抵抗力が低下します。
- 不安定感は、肘がぐらつく感じがすることを指します。
7. 力が入らない感覚
- 力が入らない感覚:
- 肘の痛みや不安定感のために、腕に力が入りにくくなります。
- 特にボールを投げる際に力が入らず、パフォーマンスが低下することがあります