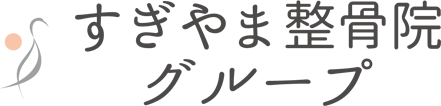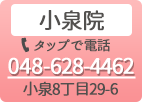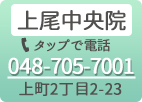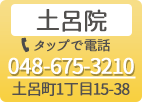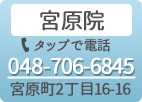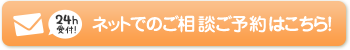過敏性腸症候群



- お腹がいつも痛い
- 便秘や下痢が続いている
- 食べ物に気を付けているのにお腹の調子が悪い
- 便秘と下痢を交互に繰り返している
- 何か月も症状が続いている
そんな症状で悩んでいませんか?これらの症状は、過敏性腸症候群(IBS)と呼ばれるもので、意外と多くの方に見られる病気です。過敏性腸症候群のせいでトイレを気にして遠くへの外出ができないなど、普段の生活を楽しめなくなるほど辛いこともあります。本当にお辛い疾患だと思います。
でも大丈夫です。我々にお任せください!
適切なケアと治療で改善したケースが多い疾患です。上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま整骨院では主に鍼灸を用いて、過敏性腸症候群に対応しています。
過敏性腸症候群の症状|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome、IBS)は、腸の機能に異常が生じ、腹痛や不快感、便通の異常(下痢、便秘、またはその両方)を引き起こす慢性的な疾患です。IBSは腸の構造に異常がないにもかかわらず、症状が現れる機能性消化器疾患の一つです。過敏性腸症候群の症状を詳しくご説明させていただきますね。
ストレス
食生活 |上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院

腸内細菌のバランスの乱れも影響していると考えられています。
腸内には、さまざまな腸内細菌が生息しています。抗生物質(抗菌薬)などの影響でそのバランスが乱れ、健康に有益な“善玉菌”が減り、有害な“悪玉菌”が増えると、悪玉菌の毒素によって腸が過敏になってしまいます。
ホルモンバランスの乱れ

特に女性はホルモンバランスの乱れに要注意です。
そもそも女性はホルモンのバランスで便秘の傾向にあります。ホルモンが体に水分を貯める作用によって大腸の水分が不足したり、大腸の蠕動運動を抑制する作用によって便秘になりやすいからです。
また一般的に女性は、男性に比べて便を押し出す力にもなっている腹筋が弱いため、どうしても便秘になりがちです。ダイエットによる食事制限などにより、スムーズな排便と良好な腸内環境に欠かせない食物繊維や水分不足によって便が硬くなってしまうこともあります。
ストレスの解消ができない
食事内容が偏っている
過敏性腸症候群に対する当院の施術|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院では、過敏性腸症候群にたいして主にまず鍼灸治療を提案させていただいております。
鍼灸は、西洋医学で言う筋肉・神経へのアプローチだけでなく、東洋医学の考えに基づいて身体全体のエネルギーの流れを整える治療法です。当院では次の流れで施術を行っていきます。
ツボ【経穴】への鍼施術

ツボ【経穴】を用いて自律神経を調整します。
過敏性腸症候群(IBS)は自律神経が不安定になり、脳が腸に適切でない伝達を送ることで症状が引き起こされます。そのため、治療においては自律神経の正常化が大きな課題です。東洋医学におけるツボへの鍼灸刺激は、自律神経への良好なアプローチが認められており、治療法として取り入れることは大変有効と言えます。関連するツボとしては以下のものがあります。
合谷

手の背面にあるツボ。主に便秘下痢など便通の問題に効きます。
曲池

肘の外側にあるツボで、大腸の問題にたいして有効。
足三里

足のすねの上にあるツボで、胃腸系のお悩み特効穴です。
三陰交

脹脛のうち側にあるツボで、冷えに対して有効です。
上巨虚

足三里から約指4本分下にあるツボで、大腸の異常に対して有効です。
太衝

足の甲にあるツボで、ストレスなどによる症状に有効です。
中脘

おへそとみぞおちのちょうど中間にあるツボで、胃腸の不調に有効です。
天枢

おへそから指3本横にあるツボで、腹部の異常に有効です。
大巨

天枢から指3本分下にあるツボで、便秘などに非常に有効です。
※こちらのツボにセルフケアでお灸やツボ押しマッサージなどを行っていくと、より楽な状態に近づいていくと思います。ぜひお試しください。
お灸施術

お灸で内臓の血流を改善します。
先述したツボなどに温かいお灸を据えることで、体内の血流を改善し、冷えを改善するとともに内臓の働きを促します。また近年では、お灸をすることで白血球が増え、免疫向上に対しても有効であるといわれています。特に上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院が使用する枡灸は広範囲を一気に温めることができますので、効果を期待できます。
全身調整

全身的な体のバランスを改善します。
胃腸だけの治療でなく、他の内臓の働きのバランスや自律神経のバランスを整える治療を行います。背部には内臓系のツボが集まっているうえに、自律神経のツボまでそろっています。ですので背中の緊張を改善することで、過敏性腸症候群によっておこる症状を軽減させることができます。
※鍼灸は、身体全体のバランスを取ることを重視するので、腸の働きを改善し、ストレス解消にもつながると考えられています。症状を根本的に改善したい方や、薬に頼らない治療を求める方には特におすすめです。
過敏性腸症候群でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。患者様一人ひとりの症状に合わせた治療計画を立て、サポートさせていただきます。
鍼灸治療の効果|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院

次に鍼灸治療での効果について簡単にお話していきますね。
腸の動きの正常化

鍼灸刺激によって血流が改善すると、内臓が栄養されることでその働きを良くし、それにより腸の蠕動運動が正常化し、便秘や下痢の頻度が減少した、という研究結果が出ています。ですので、過敏性腸症候群に限らず、多くの内踝系疾患に対し有効であると考えています。
ストレス軽減

鍼灸治療は自律神経系に働きかけ、リラックス効果をもたらします。
これによりストレスが緩和され、IBS過敏性腸症候群の症状が軽減されることが報告されています。ストレス緩和には頭部のツボが有効です。
一見頭部は怖いと感じるかもしれませんが、実は一番安全なんです。なぜなら頭皮の下には頭蓋骨しかないからです。鍼は細いので頭蓋骨には刺さりませんので、安心して受けて頂ければと思います。
痛みの緩和

鍼灸による痛みの緩和は、エンドルフィンなどの自然な鎮痛物質の分泌を促進することに関連すると考えられています。これにより過敏性腸症候群による腹痛などを軽減することができ、日常お過ごしいただくのが楽になります。
鍼灸治療は過敏性腸症候群の根本的な原因を治療するわけではありませんが、症状を緩和し、生活の質を向上させる手段として有効です。患者の症状に合わせて施術を行いますので、個々に応じた最適な治療を提供します。
よくある質問|上尾市-さいたま市北区土呂/宮原すぎやま鍼灸整骨院
Q1 鍼って痛いの?
A1 痛くありません。
鍼治療というと”痛い”というイメージをお持ちの方が多いと思いますが、体質、敏感さに応じて、鍼の太さや手技を変えて治療を行いますので決して痛いものではありません。
Q2 お灸って熱い?
A2 熱くありません。温かく気持ちいいです。
当院では間接灸といって、直接皮膚の上に行わない方法がほとんどですので、熱いというよりは温かくて気持ちが良いほどです。
Q3 鍼で病気に感染したりしない?
A3 感染の心配はありません。
当院では使用している鍼は全てディスポーザブルタイプ(使い捨て鍼)ですので感染の心配は全くありませんのでご安心ください。
Q4 どんな格好で施術を受けますか?
A4 治療用のお着替えをご用意しております。
症状によって患部だけの治療もありますが、身体全体の治療が行われることもあります。
したがって背中や足などツボを使って鍼灸治療するため、着替えをしていただく場合もありますし、そのままで行う事もあります。
Q5 鍼灸治療後はお風呂に入っても大丈夫?
A5 お風呂は入っても大丈夫です。※お悩みにより異なる場合もございます。
入浴は特に問題はありませんが、例えばぎっくり腰や捻挫など、急性の疾患で患部に炎症を起こしている場合は入浴を控えていただいてます。
その都度、治療の後に説明させて頂きますのでご安心ください。
Q6 鍼灸治療はどのくらいの間隔で受けたらいい?
A6 最低週1回を推奨しています
症状によって変わりますが、症状と痛みが強い場合などはあまり間隔を空けずに続けた方が効果的です。
慢性疾患の方は週1回ないし10日、2週間に1回で、健康管理や病気の予防などは月1~2回でご案内させていただいております。鍼灸治療にいらっしゃる際にご相談ください。
Q7 鍼が合わないとかってありますか?
A7 合わないことはありません。詳細はご相談ください。
→基本的に鍼が合わないということはありませんが鍼が合わないと思われた場合は、体質と行った治療法との相性が悪かったと思われます。
一口に鍼治療といってもいろいろな方法があリます。
施術者によっても違いはありますので自分に合う先生を見つけられるとお身体も変わって来ますので是非試してみて下さい。
Q8 何故鍼灸は効くのですか?
A8 「ツボ」に刺激を加えることによりお体の不調を早めに回復させたり、関係している内臓や器官及び組織を早く回復させてくれる効果が期待されています。
東洋医学では生体内の各器官の不調は、それに関連する体表目の神経や組織に痛み・凝り・変わった色などといった状態で現れます。
それが反応点「ツボまたは経穴」と呼ばれるところです。
鍼灸治療はその反応点「ツボ」に刺激を加えることにより成体の不調だった部分を早めに回復させたり、関係している内臓や器官及び組織を改善したりすることができると考えられています。
また、鍼や灸を行って、痛みを軽減したり、だるいなどの全身症状が改善することもできます。
Q9 どんなハリを使うの?
A9 髪の毛よりも細く、ステンレスのはりを使用致します。
※ステンレスなので金属アレルギーの方も安心安全に鍼灸治療が可能です。
Q10 ツボってなんですか?
A10 ツボは経穴とも呼ばれ、世界的に認められているものになります。
その数は361個、中には左右対の経穴もあり、全身には約700個の経穴が存在していますまた、名前や位置が特定されておらず、押したときに痛みなどの反応が現れたりしこりがあったりする場所も、ツボの一つとされます。
これらを鍼灸治療で刺激することで、身体に様々な効果をもたらします。
Q11 治療に何分くらいかかるの?
A11 当院では局所の施術ですと15分から20分、全身の施術ですと30-40分位になります。
Q12 はり治療は何回くらいうければ、効果があるの?
A16 ひとり一人お身体の症状も違うので一概には言えませんが、1回目で効果を感じて頂ける場合もありますし、回数を重ねていくことで効果を実感頂ける場合もあります。
なので、当院ではまずは最低でも5回程度の施術を受けて頂くようお願いしています。
Q13生理中も受けられるの?
A13 生理中も問題なく受けて頂けます。